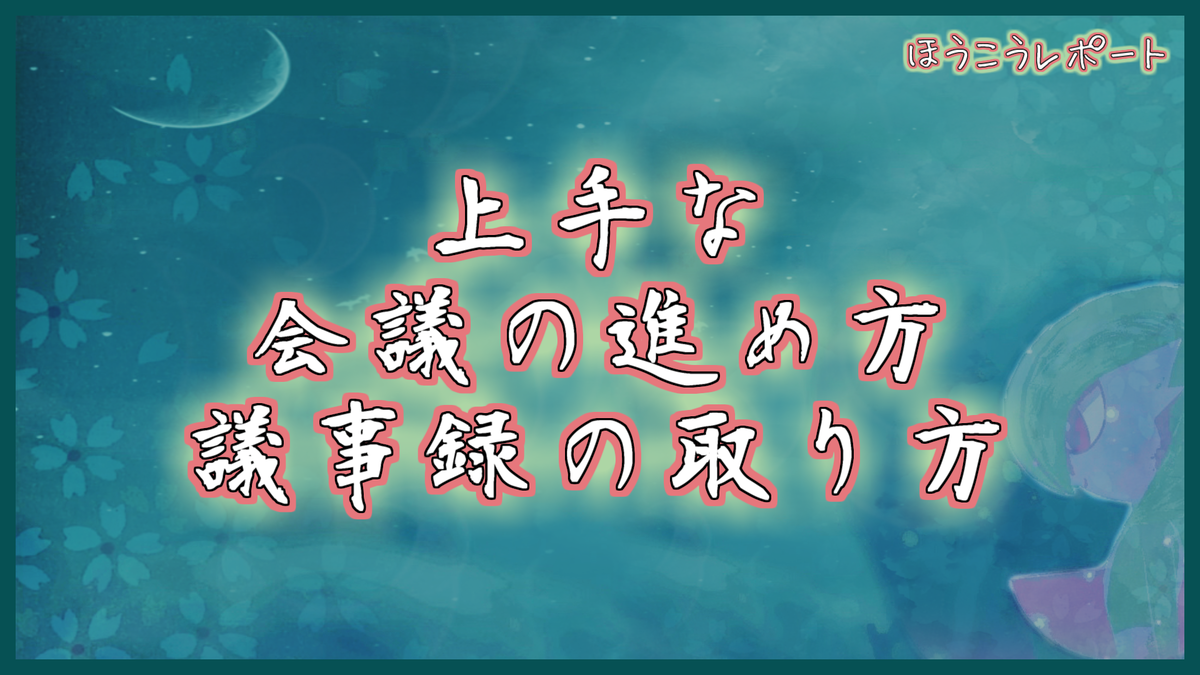はじめに
最近ありがたいことに色々と大会運営のお話をいただくので、色々な運営団体の様子を見ることができるのですが、
どの団体でも「会議」というのは大体やるものです。
運営のみんなで集まって、オフの方針だとか具体的な内容だとかを決めるわけですが、
会議に無駄がない人は最高です。
たまにいる手際がすこぶるいい主催の大会は、運営として参加していてとてもストレスがないです。
シングルでいうとぼんこふさんとか十六茶さんなんかは僕もとても信頼しています。
本記事は、会議が上手い人は何が上手いのかと共通点を探った記事です。
実際に会議上手い人から吸収して僕が使ってきた知見を紹介します。
付録として、会議に必須となる議事録の書き方についても書いておきます。
目次
エンジン役を明確にしている
会議で最も時間がかかるタイミングは2つあります。
- アイデアが1つもない状態
- いくつかに絞り込んだアイデアを一つに決定する段階
例えば、これらの状況で会議が下手な例をそれぞれ上げてみます。
会議が下手な例
①
主催「サブイベントのアイデアある人いますか?」
運営「…………(ないなぁ)」
主催(どうしよう)
②
主催「サブイベント、AとBどっちにしたいですか?」
運営「……まぁA?(どっちでもいい)」
運営「……Bの方がすきかな?(どっちでもいい)」
主催(どうしよう)
こうなってはいけない。
メインエンジン不在が故
前者の例でいうと、誰かがアイデアを1個か2個出したら解決します。
その1個か2個で決めるもよし、そのアイデアからこう改良できそうとかなんかアイデアが出たりもします。
1個も出なくても、「こういう条件のものがいいんじゃないか」みたいな内容だけでも、考えるきっかけになります。
後者の例でいうと、「いや俺はこれがめっちゃやりたい!!」と主張する人がいれば解決します。
誰かが動かせば解決する状況で、誰も動いていないから解決しないという状況です。
どちらも状況を動かす・打破するエンジン役が足りない。
では誰がエンジン役になるのかと言えば、そりゃ主催しかいないでしょう。
一番上の立場で、(多くの場合)イベントの発起人で、そのイベントをやりたいと一番思っている人なので。
会議が上手い人は、自分がエンジン役で、自分が動かさないと状況は打破されないということを認識しています。
逆に会議が上手くない人は、自分が場を動かすのを面倒くさがっていたり、運営の人が自分と違う意見だった時に嫌な気持にならないかとか心配して自分の意見を押せなかったりといった人が多いです。
打破までの時間が短ければ短いほど、会議時間も短い。会議が上手い。
とにかく、相手に丸投げしないことが主催の力量です。
尊重しすぎタイプ
面倒くさがっているだけなら、はよ決めろ!って大声出してぶっ叩いてやればいいんですが、他人を尊重しすぎてしまう人の場合は直すのがちょっと一苦労だと思います。
ただでさえ自分の大会に協力してもらっているのに、その人が自分と違う意見を持っていたら傷つけてしまうかもしれない、と思うタイプ。 ←とてもわかります。
こういう人は、自分の目的や選択理由を明確にしてみるといいと思います。
自分にはこういう目的があって、その目的を一番満たせそうだから、この案がいい。
例えば、初心者もターゲットにしていきたいから前提知識が少ないやつがいい、とか。
明確に言葉にすると、他の人も大体納得してくれるものだし、
納得しない人が仮にいたら「その理論はここが違う気がする!」と主張してくれるので、議論がひとまず進んでいきます。
とにかく、何か議論の種になるものを誰かが提供しないといけない。
この案でいいんじゃないすかと誰かが言い始めないと議論は進みません。
デカい大会でも上手に回す方法
この話をするとたまに言われるのが
「主催だけが全部決めるのはつらいよ」
みたいな話。
特にデカい大会になってくると、自分一人で全部やるのは苦しいというのもわかる。
こういう場合は、
「あなたがこの部分はエンジンになってください!」
と指定することが大事だと思います。
エンジンがいればそれが主催ではなくてもいいわけなので、これでも成り立つ。
ふんわり仕事をお願いするのではなく、「最終決定権はお前だ!」「お前がこれは全部やれ!」まできっぱり言い切らないとだめです。
ニンゲンは自分がやらなくてもいい可能性があるなら基本的には仕事をしません。
みんながそれを思って何もしない状態がエンジン不在状態なので、それを打破するためには誰かを指定する必要があります。
まとめ
誰にも頼らないか、頼るなら全力で全てを頼むとスムーズに運営できる。
中途半端に頼ると会議のエンジン役がいなくなる。
決めるべき内容を事前にリストアップしている
会議が短い人は、今日の会議のメニューを絶対に作っています。
例えば
- 日程と場所の合意を取る
- 当日の仕事分担を決める
- 備品を借りられそうか聞く
みたいな感じで。
これらの問題を全て片付けることを目的として動く。
片付け終わったらすぐ終わり。
とりあえず会議すれば話進むか~は流石に論外です。
脱線に気づける
決めるべき内容が明らかだと、脱線に気づきやすいです。
例えば会場の場所を決める話から、
そういえば~と会場マナーの記載をどうするかに話が脱線したりとか。
一見似た話題なので「脱線している」ということにそもそも気づけない場合が多いです。
会場の場所を決めるべきである!と決めておけば、
マナーの話はするべきだけどまた後で、一旦会場を決める話に戻るぞと誘導ができます。
全体会議は話を終える行為であって、始める行為ではない
そもそもの話、運営全員を集めての会議は話し合いをするものではないです。
関係者少人数ならともかく、「全員を集めて意見を聞く」というのが全体会議の意味。
小人数ではなく全員を集めないとできないことは、
内容・方針の確定
のみです。
確定、つまりその話を終える最後の役割が全体会議であって、
「会議が始まった! さぁアイデアを出して意見を募るぞ!」はお門違い。
それに、人をいっぱい集めて話し合いを始めたらそりゃ色んな会話が飛び交って収拾がつかなくなって当然というのもあります。
とにかく、全体会議は議決を取る場、話を閉じる場です。
主催ワンマンの運営なら、他の運営に自分が見落としていることがないかを確認する場。
チームで分けているなら、それぞれ考えてきたことを他のチームに確認を取って確定する場。
例えば、悪い例え。
- 「これのやり方どうすればいいと思いますか?」
- 「この件の対応をみんなで考えましょう」
みたいな感じで、今から思考を始めようとする会議はダレます。
考える人なんてエンジン役の人以外にいないので、その人以外の時間は無駄になります。
事前に考えてきたうえで、確認を取ることを会議の目標にするとよいです。
- 「これにしようと思っていますがいいですか?」
- 「この案とこの案があるんですけどどっちがいいと思いますか?/ほかに案はありますか?」
の2種類だけになるように意識すると、スムーズに進むと思います。
ex)全員が聞く必要のない話はあとでやれ!
議決を取ることだけに集中するとは言っても、
複雑な問題への対処はどうしてもみんなで話し合いながら進めたい、
とかもありますよね。そりゃそう。
こういうのは、全体の会議としてやらなければ十分です。
例えば会議でよくある話に、
「配信班の話をしている間、配信にかかわらない人は暇だけど聞いてる」
みたいなやつがあります。
これはカスです。
わざわざ集まってもらってその人が聞く必要のない話をするのは、運営効率とかではなく一般的によくないので。
なのでこういう場合は、
- まず全体で決定をする内容について、決定をする
- そのあと一部の関係者だけ残ってもらって追加で話す
とするべきです。
もしくは、その人たちだけ集めて別の日程で話し合うか。
「話し合い」と「会議」に区別をつけるとわかりやすいかもしれない。
選択肢の比較が上手い
話が早い人は、選択が上手い人だと思います。
なぜ選択が上手いのかというと、問題を切り分けて簡略化するのが上手いから。
例えば2つのイベント会場から一つを決めるとします。
ポケモンの大会で使われた例を2つ出しましょう。
トップページ - 板橋区立グリーンカレッジホール
としま区民センター
比較項目を作る
この2つだけを見てどっちにする?というのではなく、比較項目を作るのが一つ目のコツ。
見た目だけじゃわからないので、要素で比較すると早いです。
| 項目 | 板橋 | としま |
|---|---|---|
| 値段 | 安い | 高い |
| 場所 | 遠い | アクセス良 |
| 付近の食事処 | 少ない | 豊富 |
みたいな感じで、比較項目を可視化するとすぐ決まります。
目的を元に選択理由を作る
比較しただけでは、どちらもいい点がある場合に決まりきらないことも多いです。
この均衡を崩すためには、どんな目的かを考えること。
例えば、「初めてオフ会に来る人を応援したい」という気持ちを一番に掲げるとすれば、値段があまり高くなっては困るだろう、とか。
あるいは「ちょっと変わった体験を売りにするからある程度なら参加費は気にならないはず」と踏むのであればちょっといい会場を取ってみたり。
選択が早い人は、目的を意識するのがかなり早いです。
目的があれば、それに沿った意思決定ができます。
付録:議事録の書き方
会議を進めるうえで、議事録は取るべきです。
会議に来ていない人がいる場合はもちろん、喋った内容は忘れるものなので。
この議事録が上手い感じにまとまっていると、来ていない人も後から見返るときにも見やすくてストレスフリー。
会話をそのまま書かない。
よくやりがちな議事録の例。
ダメな例
景品にそんなにお金は使えないなぁ……。
トロフィーはなし。
お金かからないけど賞状だけとかは渋いな。
ぬいぐるみにしよう。
主催の好きなfitでいいんじゃない?
良い例
景品:ぬいぐるみ(fit)
・1500円以内のため他案:トロフィー・賞状
会話をそのまま書くと、
文章を文章として読まないと情報が得られない。
下の良い例であれば、
「景品」「ぬいぐるみ」「1500円以内」
と、情報に必要な単語だけを読み取れる分理解が早くなる。
整理された単語を置くことを意識するだけでもかなり変わります。
とにかく、議事録は会話ログではない。
一問一答を意識
話題一つに対して、結論一つを書くだけ。
これが議事録の基本です。
ダメな例
何人くらい入る会場にするか
・よくある大会は64人規模
・今まであまり大会に来ていない、初心者層も取り入れたい
・友達を誘ってもらうように呼び掛ける
・ちょっと多めにしてもよさそう
いい例
何人くらい入る会場にするか
→80人規模にする
・よくある大会:64人規模
→初心者層を追加するため、少し多めに
Q:会場の規模は?
A:80人にする
とすっぱり解答を書いているのがポイント。
この一問一答を積み重ねることで議事録を作ると、パッと見てわかりやすい議事録になる。
逆に言うと、そもそも何を決めるかという問いがしっかりしていないと一問一答は作れない。
また、だらだらと脱線した状況で話していても、問いが分からないので一問一答は作れない。
一問一答を作ろうという意識で会議をすると、自然と会議に無駄がなくなっていくと思う。
他の選択肢は書くだけ書く(詳細な内容は書かない)
後から「やっぱ他にもいい選択肢はないの?」となったときに見返すのも議事録の役割。
前述の二項で内容の無駄を削れという旨をたくさん言ってきたものの、削りすぎはやっぱりよくない。
長くなりすぎない程度に、採用案以外の候補も書いておくと吉。
いい例
大会の名前:××
候補:○○、△、★★
選択理由を短く書いておく
上と同じく、
なんでこれ選んだんだっけ?となったときに見返せるようにするととてもよい。
理由まで書くとかなり長くなってしまうので、
- 一文に留める
- 議論が白熱したもののみ、理由を書く
など対処が必要。
いい例
大会形式:スイスドロー
ダブルエリミ
→対戦回数が少なすぎて消化不良になる人が出る
ガンスリンガー
→誘導要因足りない
最後にタスクまとめを作る / 誰がいつ何をするか
議事録の最後に、与えられたタスクをまとめておく。
いわゆる5W1Hってやつかもしれない。
これがあるだけで、議事録全体を読み返さずとも自分の役割が分かるのでかなり神。
リマインダーにもなる。
なんなら会議自体のまとめにもなるので、これをやるのが一番大事まである。
皆さんも次の会議では
↓のような感じで最後にタスクまとめを作ってみてください。
めっちゃ分かりやすくなっておすすめです。
いい例
クロサナ
・要綱を書く →7/12まで
・Discordサーバーを作る →7/6までゴルリア
・名札を描く → 8/3までズバトス
・募集フォームを作る →7/6まで
改行・記号を多く使う
ここまでくるとかなり細かなテクニックになりますが。
議事録をより見やすくするには、
- 改行でブロック分けしてやる
- 記号で見出しを分かりやすくする
などがあります。
もちろんWordなど文字の大きさ変えられたりするならまぁそれに越したことはないです。
改行とか
~~~
で区切るとか
区切り目を分かりやすくすると視認性がかなり変わるのでおすすめ。
おわりに
主催がエンジン役になれ!!!
主催が決定するか決定権を委任すること!!
主催以外の運営はそこまでやる気はない!甘い期待をするな!
これだけ覚えておいてもらえたらたぶんいいです。
他の運営を頼るのは必要だけど、何も言わなくても動いてほしいなんて甘えてはいけない。
甘えていない主催がいい主催。